氷川省吾
“昼なお暗き”という言葉が、この上なく適切だと思わせる場所だった。
東北のある山の中。カーナビもろくに場所を正しく示せないような山道を上り続け、篠田邦彦が運転するSUVは、ようやく目的の場所に到着した。高速道路から降りてから、すでに4時間が経っている。周囲には縄文人がこの地を歩いていたころから変わりがないのではと思わせるような原生林が生い茂り、本来ならば見えるはずの山肌を完全に覆い隠していた。太陽は頂点に近い場所にあるはずだが、好き放題に枝を伸ばした常緑樹の葉が覆い隠し、降り注ぐ光の強さを半減させている。
クマやサルどころか、得体のしれない妖物の類さえ出てきそうに思える。これに比べれば、熊野古道さえハイキングコースに見えてくるほどだ。道はかろうじて車が1台通れるだけの幅しかない。アスファルトではなく石畳が敷かれており、これがかろうじて植物の浸食と土の流出を防いで、道を存続させている。ナビもスマホも機能しない状態で何とか迷うことなくここに来ることができたのは、車が通れそうな道がこれ以外なかったことだけが理由だ。
誰がこんなところに住んでいるというのか。
到着するほんの僅か前まで篠田はそう思っていた。だが実際に着いてみると、どうやら人がいることだけは確かだということが分かった。家がある。非常に立派な家だ。
古びているが高さが3m以上もありそうな塀が立っており、その向こうに茅葺の大きな屋根がそびえている。このご時世にこれだけ立派な茅葺の屋根が残っている場所はそう多くない。
「ここ……、ですよね? 先生」
助手席に座っていた花本詩織が、高精度GPS機能の付いたナビの画面と、目の前の光景を見比べながらつぶやいた。この場所ではナビがあったところで住所を正確に示してくれるとは思えない。緯度経度を入力した方がまだ確実だろう。
だが、他に人が住むことができる場所があるとは思えない。篠田はここで正しいのだと結論付けた。
「多分、そうだろうね。多分」
篠田は車を少し前に進ませ、駐車できそうな場所を探した。ここに警察が駐車違反を取り締まりに来るとはまず考えられないし、通行の邪魔になるとも思えないが、道の真ん中に放置する気にはなれなかった。門は閉まったままだったが、すぐ横に空き地が作られ、プレハブのガレージが置かれていた。シャッターが閉まっていたが、前に一台ぐらい止めても問題はなさそうな余裕があった。
篠田はそちらにSUVを寄せて止め、エンジンを切って車から降りた。8月の最中ではあったが、冷房の効いた車内から出たにもかかわらず、暑さはほとんど感じなかった。“下界”のうだるような熱気から完全に切り離されている。
「すっげえ場所にすっげえ家」
助手席から降りた花本が、家の様子を見て呆れたように言った。車から降りて目線の高さが下がった分だけ、塀がさらに高くなったような気がした。真っ黒に見えるほど年月を経た杉板で作られた門が、正面に構えている。非常に古いが、中型トラックで突っ込まれでもしない限り壊れそうにない。
「これって、実は誰もいませんでした、なんてオチは無かったりしませんよね」
花田の言葉と目の前の光景から、篠田は「迷い家」という話を思い出した。旅人が山中で大きな黒い門を持つ立派な家にたどり着くが、中に入っても人が誰もいない。つい先ほどまで人がいた痕跡があり、湯気の立つ湯飲みが座卓に置かれ、火鉢の炭は火が熾されて、鉄瓶の中で湯が沸いている。あたかも旅人が入ってきた瞬間に、家人が姿を消してしまったかのように……。
結局、不気味さを感じた旅人は逃げてしまうのである。オチはいろいろで、この時にもらっていった器で米を掬ってみると、米がなくならなかったというパターンの他、もう一度行ってみようとしても見つけられなかったというパターンもある。いずれにしても、山中に無人の立派な家が忽然と現れるという点では同じだ。
住人からメールで依頼を受けて来訪したのでなければ、迷い家伝説は現実にあったのではないかとも思わせてしまうような雰囲気がある。ただ、車が停められそうなガレージがある以上、住んでいるのが山姥や天狗の類ということもあるまいと思われた。現代日本に生きている人間だろう。
門に近づくと、横にインターホンが取り付けられているのが見えた。年季が入った杉の板に、グレーのプラスチックでできたカバーが張り付いている。その有様は、古びた時代に迷い込んだ、機械仕掛けの奇怪な甲虫のようにも見えた。そのすぐ下に、目立つ赤色に塗られた郵便受けが取り付けられている。今も人が住んでいるとアピールしているようにも見える。
篠田はインターホンのボタンを押した。しばらく経って、もう一度押そうとしたとき、スピーカーが繋がったことを示す空電音が聞こえた。
『……はい』
篠田の予想とは異なり、若い女性の声だった。メールの送り主の名前は確かに女性の名前だったが、もっと年を取っているはずだと思い込んでいたのだ。
「すみません。北東大学自然人類学研究室の篠田です。こちらは八瀬様のお宅でしょうか?」
『……お待ちしておりました。戸は開いておりますので、どうぞお入りください。母屋にてお待ちしております』
インターホンが切れると、篠田と花本は顔を見合わせた。
「ここで合っているのは間違いない」
「少なくとも人が住んでいることも、ですね」
文明の利器越しに人の声を聴いてからも、まだ化かされたような気妙な気分が付きまとっている。ひとまずそれを横に置き、二人はSUVのトランクから今回の“作業”に使うための道具を取り出した。
「先生の研究室に入ってから、こういう場所に来るってのはちょっと予想外だったかもです」
トランクに入れていたクーラーボックスを引っ張り出しながら、花本がそんなことを言った。
「たいていは博物館とか研究室に行くからね。こっちから出向くってのはあんまりないな」
篠田はカメラ一式と照明器具、撮影用ブースボックスのセットを取り出した。
篠田は北東大学の自然人類学研究室で助教授の職に就いている。自然人類学は自然科学の分野から人類の進化や歴史を読み解く学問で、発掘された骨や歯の形態を分析することで、その持ち主がどういう人間でどういう生活を送ってきたのかを調べ上げる。
石器や食事、入れ墨、装飾品などの文化的な情報の他、DNA解析や炭素年代測定、CTや3Dスキャナーまで利用することで、たとえ数千年前の遺体であっても年齢や顔、肌の色、目の色、食習慣、持病、当時の流行りのファッションに至るまで明らかにすることが出来てしまう。
そうやって人類の歴史にメスを入れていくことが、この学問の目的となっている。
他の研究分野と同じように、自然人類学も多数の専門分野に分かれ、どの場所で、どの年代の人間を相手にした分析を行うのかは異なっている。600万年前のアフリカに生きていた猿人を専門とする学者もいれば、江戸時代の大名の遺体を研究する学者もいる。
その中で、篠田は古代から近代にかけての遺骨やミイラの分析を専門としている。工事の際に地面を掘り起こしたら江戸時代の墓場だったので骨を何とかしてほしいとか、博物館に収蔵されている化石を再検査してほしいとか、古い骨がらみの話は意外と多く、技術提供のために海外の大学や研究機関と共同研究を行ったこともある。
ただ篠田の場合は人間の遺体に加えて“怪奇”に造詣が深い。河童に天狗に鬼に化け物。人魂に死人憑きに妖怪に至るまで、仕事の間にあらゆる怪奇譚を読みふけり、小学校のころから水木しげるファンクラブに入っていた筋金入りとして知られている。
そんな人間なので、彼の元にはいろいろと胡散臭い話が入ってくることがある。河童のミイラだの鬼の角だの、宇宙人の指なんてものまで、持ち主が正体を確かめてほしいと思ってどこかの大学に鑑定を依頼すると、それがなぜか篠田の方に話が流れてくる。
篠田の方も物好きなので話に食いつき、あれやこれやの手で教授と委員会にねじ込んで予算を取り付け、嬉々として出かけていく。もっとも、それが本当に河童や鬼の持ち物とは思っていない。持ち主からいろいろな話を聞く方がメインなのだ。
分析すれば結果はほぼ100%、つまらないものにしかならない。小動物のミイラの継ぎ合わせ、牛の角の加工品、ただの石ころ。それを野暮としてしまうか、それとも大したことがないものに尾ひれがついた工程を考える楽しみができると考えるかは人によるが、篠田は常に後者の考え方を取るようにしていた。
今回の話も、そうした経緯で持ち込まれた案件だった。
紹介してきたのは篠田の旧友の法学医で、骨の鑑定仲間ということで知り合っている。依頼者の名前は八瀬雪緒。見てほしい物品は「鬼の頭蓋骨」。
メールに記載されていた住所を検索した篠田は、そこがとんでもない山奥であることに驚いて断ろうとも考えたが、添付されていた写真を見て考えを改めた。
一目見てわかった。偽物だろうと何だろうと、これは現物を調査する価値がある。
そうやって長い時間をかけて山の中までやってきた篠田は、ようやくメールの送り主と対面できるところまで来た。花本の方はそろそろ論文のテーマを決めようかというところで、うまくいけば篠田が関わっている剣に相乗りさせてもらえるかもしれないと踏んでいる。
戸をくぐると、その先には石畳と玉砂利が敷かれた広い庭と、その先に立つ茅葺の母屋が見えた。敷地の広さは3千坪ほどもありそうだ。ちょっとした旗本屋敷ほどもある。母屋の方も、一家に加えて使用人家族が住んでもまだ余裕がありそうに見えた。それ以外にも様々なものがありそうだが、一度にすべてを見渡すことは出来そうになかった。
ひとまず、篠田達はインターホンからの言葉に従って正面の玄関に向かった。ドアは近代的なガラス入りの引き戸に変えられている。縁側も障子ではなくガラス戸が入っていた。迷い家ではないのは確かそうだ。
篠田が玄関横にインターホンがあるかどうかを探そうとしたとき、戸が横にひかれた。
そこに立っていた人物――インターホンの声の主を見た時、篠田は思わず目を見張った。
声の通り若い女性だった。年のころは20代半ば。背は170少々の篠田と同じぐらいで、女性としては高い方だろうか。夏物の暗い色のブラウスと紺色のロングスカートの姿が、背の高さと体格の細さを強調している気がした。
篠田が目を奪われたのはその顔立ちだった。整った細面の顔立ちの中で、切れ長の目が篠田と花本の方を見据えている。化粧気は無いが、白い肌とうっすらと赤い唇の対比が目を引いた。女優やアイドルのような華美さではなく、肖像や写真のモデルが持っている彫像のような美しさがあった。
「暑い中、ありがとうございます。この度、ご依頼をさせていただきました、八瀬と申します」
「は、はい。北東大人類学研究所の篠田です。こちらは院生の花本です」
予想もしていなかった相手の登場に、篠田の声が思わず上ずった。
「よろしくお願いいたします。それではこちらへ」
篠田の様子にも眉一つ動かすことなく、八瀬は二人を仲へといざなった。玄関は広さが8畳もありそうだったが、靴が入っている棚の中にあったのは数足だけだった。どれも女物で、スニーカーやサンダル、それとパンプスが1足ずつ。この家に住むのが八瀬一人だけであることを示していた。
靴を脱いだ篠田達は、広い屋敷の中の奥にいざなわれた。薄暗い家の中で、八瀬の背中まで延ばされた全く癖のない黒髪に光が反射して見える。
「立派なお家ですねえ」
花本がそんなことを言うと、八瀬は振り返ることもなく答えた。
「先祖から受け継いでいる家です」
「失礼ですが、お一人ですか?」
「現在は私一人だけです。家族もおりません」
「こんな広いところに一人……」
「定期的に庭師さんや業者の方に手を入れていただいているので、何とか維持できております」
花本の質問に、八瀬が簡潔で事務的な答えを返すやり取りが続き、やがて篠田達は客間の一つに案内された。12畳の大きな部屋で、真ん中には杉の一枚板を使った大きな座卓が置かれている。
「こちらでお待ちください。すぐに持って参ります」
そうして、八瀬はしずかにどこかへ部屋を出てどこかへと行った。
残された篠田と花本は、なんとも言えないあっけなさを感じながら、いそいそと準備を始めた。まずはビニールシートを出して座卓の上に敷く。標本と机を汚したり傷つけたりしないようにするためだ。
「先生、あれですよ。来てよかったんじゃないですか?」
シートの上に撮影に使うブースを置いて展開しながら、花本がそんなことを言った。
「あの写真を見たからね。確かめたくもなるさ」
「いや、そうじゃなくって。出迎えてくれたのがすげぇ美人だったってこと」
「そっちか」
「あんな美人さんがこんなところで一人暮らしって、何か気になっちゃいますよね」
これが東京の高級マンションならともかく、こんな辺鄙というには辺鄙すぎるところで、不自然なまでに立派な旧家屋で一人暮らしているとなると、訳ありめいたものがあるような気がする。ただ、それをいちいち尋ねる気はさらさらない。誰にだって事情がある。それを根掘り葉掘り聞こうとするのは、河童のミイラの正体が作りものだったからと騒ぎ立てるよりもはるかに野暮だ。
「そういうことは胸の内にしまっておくんだね」
撮影の準備が整い、篠田と花本は用意してきた使い捨てのラテックス手袋をはめた。手垢や皮脂などに含まれるDNAが、検査対象を汚染することを防ぐためだ。
そうしているうちに、八瀬が戻ってきた。手には木箱を抱えている。机の上に敷かれたシートを見て一瞬だけ怪訝な表情を浮かべた気がしたが、意味を理解したのかすぐに元に戻った。篠田はこの女性が人らしい表情を浮かべるのを見て、何か安心したような気になった。
「こちらになります」
八瀬が箱を机に箱を置いた。高さは40㎝程度で、縦横は30㎝ほど。ちょうど人間の頭が入るサイズだ。材料は桐らしく、丁寧なつくりをしている。ふたには特に何も書かれていない。こうした類の物ならば、どこかに中身の詳細や日付が描かれてあるようなものだが、そうではないようだ。
篠田の視線を知ってか知らずか、八瀬は高級な料理の皿に被せられたクロッシュを外すように、箱のふたを開けた。
“それ”を眼にした瞬間、篠田と花本の口から感嘆の声が漏れた。
紛うことなき「鬼」の頭蓋骨があった。
“それ” は人間の頭蓋骨でありながら、明らかに異なる特徴を有していた。
本来ならば滑らかなドーム状となっているはずの前頭骨に、一対の大きな突起が形成されている。まさに“角”だ。
位置は両方の眉よりも上、人間でいえば生え際のやや下あたりになる位置だろうか。特大サイズの猛禽類のカギ爪といえる形状をしており、長さはそれぞれが10㎝程度、太さは付け根が4㎝程度ある。左側の角の先端部は折れて短くなっていたが、残った右側はスチール缶に風穴を開けられそうな鋭さを有している。
異常なのは角だけではなかった。眉の根元にあたる位置は、眼窩上隆起を思わせるほどに上眉弓が発達している。人間の眉毛の内側と鼻の付け根にかけての部分の張り出しが大きく、非常に彫が深い顔立ちになっているのだ。コーカソイド系やオーストラロイド系の民族に近いが、それよりも張り出しが強く、そのせいで骨そのものが眉をしかめているような形状になっている。般若面の様だともいえるし、威嚇する獣の顔立ちともいえた。
さらなる異様さを感じさせるのは口元と顎だった。歯並びはかなり悪く、数える限りで八重歯が15本以上ある。さらに犬歯の発達が著しく、口を閉じていても覗きそうなほど長くなっている。全体的な印象から見るに、元から長かった物がせり出してきたような雰囲気がある。
顎そのものも相当な重量感を持ち、正面から見ると頭蓋骨のアングルがほぼ四角形を成するほど発達している。肉がついていればさぞかし厳つい顔立ちになったことは想像に難くない。
篠田は顔を近づけ、細部を入念に確認した。全体の色はクリーム色がかかっており、そこまで古い骨でないことを示している。骨格標本などとも異なり、特に漂白処理なども施されていないようだ。
普通の人間とは異なる部分――特に角の周辺を確認してみたが、はっきりとみてわかる継ぎ目はない。頭骨と角の色合いもほとんど同じだ。角を境にして頭骨との色が異なっていれば別の生き物の骨を継ぎ接ぎして作ったことは明らかだが、その様子もない。
技術さえあれば、組み合わせの痕を処理して細工を施すことで、本物に極めて近いフェイクを作り出すことは可能だ。江戸時代には水牛の骨を加工して膠で貼り付けて組み上げることにより、本物と見紛うばかりの“象の頭骨”を作った細工師がいたとされている。彼に依頼した人間は、この奇妙な贈り物を賄賂にして出世の手掛かりにしたとかいう話がある。
篠田はこれまで、いくつかの“鬼の骨”を見てきた。岐阜県の念興寺に収められている鬼の頭骨。大分県の十宝山大乗院に収められている鬼のミイラ。ただ、前者は角の取り付けに不自然さがあり、他の部分はただの頭蓋骨だった。後者は形状が明らかにおかしく、X線検査で作り物と判明している。
それらに対し、この頭蓋骨は異常でありながら自然だ。いかに異形であっても、動物の体を構成するのであれば一定の自然な印象がある。優れた才能の持ち主が描けば、空想の動物であってもまるで実在している動物を描いたかような自然さを作り出せる。それは生き物としての自然を作るなポイントを押さえているからだ。
この頭蓋骨を作った者は、非常に優れた細工の技術に加え、生き物らしさを生み出すポイントを完全に把握していたのに違いない。
現代まで残っている河童や天狗や人魚やらのミイラは、いずれも動物のミイラをつなぎ合わせて作った偽物で、中には死体すら使用していない完全な人形まであった。どれもが見世物小屋の展示品や土産物として作られているものだが、優れた作品は本当の死体ではないかと思わせる自然な仕上がりになっている。
たとえフェイクであることが判明しても、出来の良さが衰えることはない。この頭蓋骨もその一つ、あるいはそれ以上とも言える代物だった。
「これはすごい」
篠田ははっきりと口にした。美術の素養は無いが、それでもこの頭蓋骨が工芸品どころか芸術品としての完成度を持っていることは確かだ。
「これ本物だったりしませんか?」
花本がそんなことを言い始めるほど、この頭蓋骨の出来栄えは自然で真に迫っていた。
「これの由来については、私は特に家族から何か聞いたことはありません。鬼の骨があるということは子供のころからきいていましたが、目にしたのは成人してからのことです。子供に見せるには、あまりに……、気味が悪いというのもありますし、なんとも不吉な物ですから」
「ごもっともです。触れても良いでしょうか?」
「どうぞ」
八瀬の許可を得た篠田は、頭蓋骨にそっと触れた。ラテックスの薄い手袋越しの感触で、この髑髏が木やプラスチックではなく、本物の骨で作られていることが分かった。
篠田は頭蓋骨の前頭骨と頭頂骨の境目を指でなぞった。人間の頭蓋骨は45個ものパーツから成り立っている。赤ん坊の時は狭い産道を通り抜けられるようにパーツがまだ癒着していない状態だが、成長するにつれて間にある組織が骨化して固まっていく。このパーツ同士の境目が、骨が固まった後でも縫合線と呼ばれる継ぎ目となって残る。
違う骨同士を組み合わせるなら、この縫合線のところでつなぎ合わせれば最も自然に見える。相当に高い技術を使っているようで、縫合線のところは自然に見えた。隆起している眉の付近や角の付け根を含む前頭骨とその他のパーツの境目はやや盛り上がっているように見えるが、はっきりとつなぎ合わせと分かるレベルの物ではない。研究室に持って帰って、表面のサンプル素材を取ったり、顕微鏡などで精査したりすれば、作った方法が明らかになるはずだ。
もっと詳細に観察をしたかったが、それは我慢した。最低限の仕事をすます必要がある。
まず骨を撮影ブースの上において照明を点けた。後ろと左右に立てられた白い板が骨の後ろまできれいに照らして、全体が明るく映るように設定する。横にサイズの目印になる定規を立てて、花本が前後左右の状態を撮影した。一眼レフのシャッター音がするたびに、頭蓋骨が反応しているかのような気がする。
写真を撮るのは学術的な記録だけでなく、これからこの骨を借り受けるにあたっての状態を記録しておく法的な意味合いもあった。あらかじめ取り決めた以上の破壊をしないようにするという宣誓のようなものだ。
可能ならば所有者の立ち合いがある方が望ましかったが、いつの間にか八瀬の姿が消えていた。こちらが骨に夢中だったせいもあるかもしれないが、出ていく気配がまるでなかった。
「いやあ、それにしてもすごいお金持ちですよねえ」
骨の入っていた木箱の写真を撮りながら、花本が呆れたかのように言った。
「すごい家だし、それで定期的にメンテしてもらってるんでしょ? こんなデカい一枚板の杉の机なんて見たこともないし。由緒ある家系ってやつなんですかね」
「まあ、そうなんだろうな。この骨に関係があるなら話してくれるかもしれんが、あまり詮索しなさんな」
「いやあ、それでも気になりますよ。お金持ちなのに、こんなところで一人っきりって」
なんとも居心地の悪い思いを抱きながら作業を続け、一通りが終わったとき、ふすまが開いて八瀬が姿を現した。手にはグラスと茶菓子が乗った盆を持っている。
「お疲れ様です。碌なおもてなしも出来ませんが、こちらをどうぞ」
機材を片づけ、骨を元通り木箱に戻すと、八瀬がグラスと茶菓子を机に置いた。グラスにはよく冷やされた緑茶が入っていた。小皿にはカットされた水羊羹が乗せられている。先ほど姿がいつの間にか見えなくなっていたのは、これを準備していたからのようだ。
作業中には使わなかった分厚い座布団に座って出された品を口にすると、“金持ち”という花本の言葉の正しさがよく分かった。茶も水羊羹も、高級品とは縁遠い篠田の舌にも上等なものであることが分かる。どこか有名な店の品だろうとは思ったが、黙っておくことにした。
「これおいしいですねえ」
篠田の思いを完全に無視して、花本が上機嫌にそんなことを言った。皿の上にあった水羊羹のほとんどが消えている。
「お口に合ってよかったです」
特に表情を変えることもなく言う八瀬に、花本が何か言い始める前に、篠田は話を鬼の頭蓋骨へと持っていくことに決めた。
「こちらの“鬼”の骨について、詳しくうかがってもよろしいでしょうか? 由来をご存じないとのことでしたが、それ以外についてでもご存じのことがあれば」
八瀬の視線が篠田の方を向く。黒曜石のように見える瞳にみられ、篠田はわずかに心臓が跳ねるのを感じた。
「はい。経緯についてはメールにて送らせていただいた通りになります。あの骨は祖母が子供のころからあったという話だけを聞いております。誰がどこで手に入れたなどの話はありません」
「なるほど」
定期健診の際に、レントゲンを撮っていただいた先生と骨のお話をしたときに思い出して話すと、そうしたことに詳しい人がいるとのお話を伺ったので、ご連絡をさせていただいた次第になります」
篠田は紹介してきた医者のことを思い出した。あの人物がこんな人と知り合いというのは意外な気もしたが、世間は狭いということか。
「なるほど。他に関係がありそうなことなどはありますか」
「実は、我が家は昔から“鬼八瀬”と呼ばれることがありました」
「ほう」
思わず篠田は身を乗り出した。変わった物の調査を行う中で、こうした昔のことを聞くのが醍醐味の一つになっている。
「こちらは祖父母からきかされた内容ですが、戦前あたりまでは、八瀬の家は鬼の血が混じっているとか、それで鬼になって狂死するとかのうわさが立っていたようです」
「昔の人は嫌な話しますね」
花本が呆れたとでも言いたげな声を出した。
「それで、集落から離れたこんな場所に家を建てたようです。お金はあったので村八分扱いでも生活に困らなかったし、それをあてにして他からお嫁に来る人がいたから、今まで残ってきたようです」
篠田はその話を聞いて、思い当たる節があった。
「失礼な言い方になるかもしれませんが、“憑物筋”のような扱いであったということでしょうか?」
「憑物筋……。ある意味、そうかもしれませんね」
「先生、憑物筋って何ですか」
花本が学生よろしく手を挙げた。
「憑物ってのは憑依する霊とか狐とか蛇とか、そういう怪しい物のことだよ。そいつがどっかからやってきて誰か憑くんじゃなくて、家――家系に憑いている血筋が憑物筋って呼ばれていた」
「憑物筋の者は自分の家系に憑いている狐や蛇、狗神などを使役して、他所の家から物を盗んでこさせたり、敵対すれば病気にしたりすることがあるとして、昔から嫌悪の対象になっていました」
篠田の言葉を八瀬が継いだ。彼女の語り口は、それが民俗学的な事例よりもっと身近な事である様子をうかがわせた。
「憑物筋と言われる理由は、一番多いのは“僻み”だよ。どこかよそから来た人がいて、それで商売をうまくやって金を持ったとすると、他の連中はそれを僻んで “俺たちが同じようにできないのは、あいつが俺たちの金を奪っているからなんだ”と言い始める。怪しいお祓い坊主やら似非山伏やらがやってきて、それに何か理屈をこじつければ、憑物筋の出来上がり」
「陰湿な上にセコイですね」
「閉鎖的な環境が作る、悪い部分の代表例って感じだね」
「実際にこの家の祖先は、近隣の村――とはいっても山一つは離れておりますが、そちらとはほとんど関係のない地域から来た者であったようです。実際にどこから来たのかについては全く分かっておりません。どうやら鉱山に関する知識や金細工の技術があったらしく、それが財を成す礎になったようです。憑物筋と同じ扱いをされる背景は備わっていたということになります」
「憑物と言えば狗神や狐、オコジョのような管狐やイサキ、あるいは蛇などといったところなので、鬼憑きというのはまた変わっていると思っていました。なるほど、鉱山や金細工の関連ならばあり得る話ですね」
「先生、意味わかりません」
またも手を挙げる花本に、篠田は若尾五雄という人物が、『鬼伝説の研究』という本でまとめた説について話した。この説は、日本各地の鬼伝説地が鉱山地に多いことを指摘し、伝説中の鬼が話中で金工に密接に結び付いている例も少なくないことから、鬼が金工師をモチーフとしているのではないかとしている。実際にこれだけで鬼の起原全てを説明するのは無理だが、イメージ形成の中で大きな役割を担っていることは想像に難くない。
つまり、よそ者としてやってきて、金工で財を成した八瀬の先祖が、鬼の子孫であるとされて憑物筋のような扱いを受けたのは理由としては十分にあり得る。
「ただ、あの骨については、それと関係がある話はありません。もしかすると、我が家が鬼八瀬であることに関連付けようと、誰かが面白半分に作らせたのかもしれませんね」
そのあとも、篠田と八瀬は鬼と憑物についての話をつづけた。篠田は彼女が当初の印象と異なっていろいろと話をするのを意外に思った。しゃべる際にあまり口を動かさず、表情の変化も大きくないので無機質な雰囲気は残ったが。
「先生、そろそろお暇しないと」
携帯に目を落とした花本が、篠田と八瀬の会話に割って入った。篠田も自分の時計を見ると、すでに夕方になっていた。これから山を下りる間に夜になってしまうとかなり危ない。後ろ髪を引かれる思いだったが、さすがに帰らざるを得なかった。
「ああ、すみません。長居しすぎました。骨はお預かりして、詳細な検査を行います」
篠田は書類を出して説明した。2か月の預かり証と、これから行う予定の検査の内容を記した書類にサインをもらった。緩衝材を詰めたクーラーボックスに骨と箱を収め、篠田と花本は山中の屋敷を後にした。
「やっぱり来てよかったですね。美人さんと話が合って」
「まだ言うか」



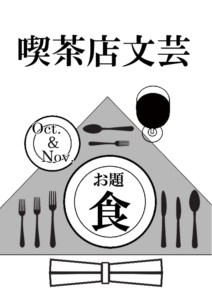

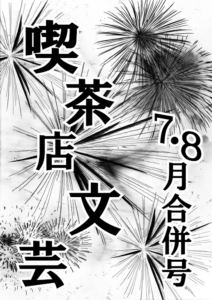
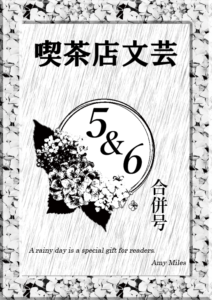


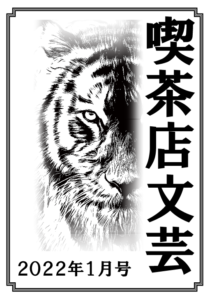
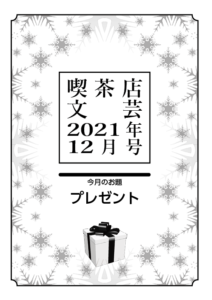
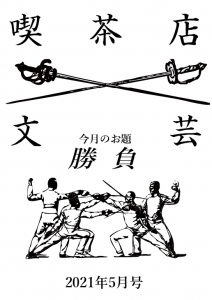
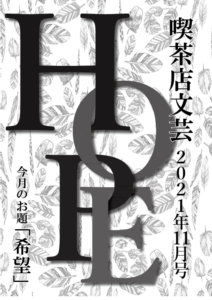
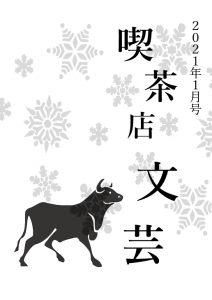
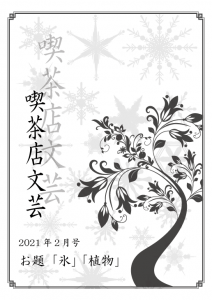
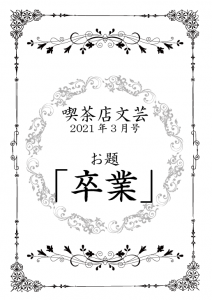
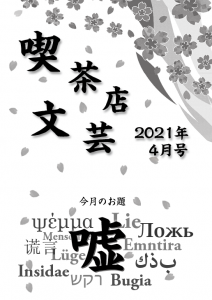
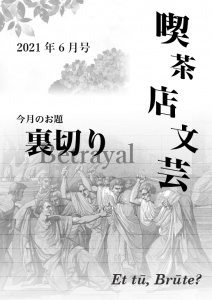
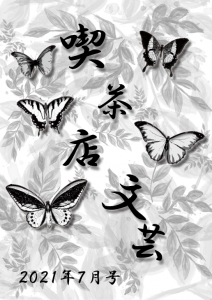
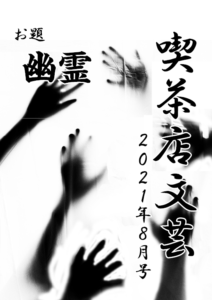

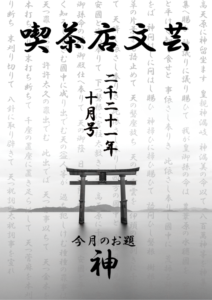
コメント