榊はモニターに表示された3Dモデルを見た。これがつい先日、完成したばかりの成果だ。ある種のタンパク質複合体の立体構造図。サンプルの発見からこの図が作られるまで、4年もの時間が消費されている。それほどまでに巨大で複雑な物だ。榊がスカウトされたのも、これを完成させて研究を次のステップへと進めるためだった。
サイズは1つのタンパク質分子としてはかなり大きく、0.8マイクロメートルほどもある。既知のタンパク質で最大なのは、筋肉の収縮に関わるチチンだ。中でも人間の物が最も大きく、長さが1マイクロメートルを超える。
このタンパク質はそれに近い大きさがある上、構造は遥かに複雑だ、条件によって立体構造が変化し、場合によってはちぎれたり連結したりする。まるでクダクラゲのごとき群体生物なのかと思うほどだが、あくまで生物ではない。タンパク質なのだ。生き物の体を機械に例えるのであればネジやナットなどの部品に相当するはずなのだが、それでいて生物のように振る舞う。
この上なく不自然な存在だ。宇宙人が作ったとか、異次元の生態系からやってきたとか言われると納得できてしまえるほどに。
あり得ない存在。単にそれだけなら問題はない。世紀の発見として発表してもいい。問題はこれが人類史上どころか、地球史上最悪クラスの病原体であることだ。対応策を研究する必要さえなければ、存在するサンプルを全て核兵器で焼却した上で、灰を固めて日本海溝へ沈めるべきだと榊は考えていた。
この病原体は他のタンパク質と接触することで構造を変化させ、自分と同じ形に変えてしまう。動物の体内に入ると体の部品を自分の複製にして増殖していく。
同様の性質は、牛脳海綿状症(BSE)やクロイツフェルト・ヤコブ病の原因となる異常型プリオンが有している。この異常型プリオンは脳の中にある正常なプリオンの形状を自分と同じ物に変えることで増えていき、脳に非常に微細な空胞を作り出すことで牛や人を死に至らしめる。
この病原体の性質もそれに近いが、対象にするアミノ酸やタンパク質の種類が多岐にわたり、脳に限らず体のあらゆる部分で増え、組織構成その物まで作り替えていく。
モニターの中に見える3Dの構造図は、赤や黄色のリボンや突起のような物が複雑に絡まり合った、訳の分からない物にしか見えない。初心者が作ったCGアートの様だ。これを見出すのにどれほどの労力が費やされたことか。だが、必ずや成し遂げなくてはいけない事でもある。戦うためには敵の正体を掴まなくてはいけない。
榊がいる第1研究室は、生化学や分子生物学、構造生物学といったミクロの観点から病原体を研究する。感染した後の生物を病理学や生理学、解剖学的な観点から研究するのは第2研究室が行っている。研究室同士は物理的に離れているが、情報の共有は緊密に行われている。なので、榊はこのタンパク質が生き物の体の中に入った時に何を引き起こすのかをよく知っていた。
このタンパク質は体重300g以上の大きさを持つ動物であれば、何にでも感染する。人間以外に、犬や猫、さまざまな家畜も感染対象になる。世界中に大量にいるネズミ、どこにでも飛んでいける鳥、海を自由に泳ぐ魚。一度外に漏れだせばそうした生き物に乗って、世界中のありとあらゆる場所へと運ばれていく危険性がある。
感染の経路は主に体液感染だ。感染生物からの咬傷・搔傷、粘膜や傷口に対する感染生物の体液の接触で感染する。感染率及び発症率は100%。現在のところ、例外は発見されていない。
こいつに汚染された生物と、それらが垂れ流すものは須らく感染源になる。イワシをフライにして食べてもアウト、乾燥したハトの糞の欠片を吸い込んでもアウト、ネズミに咬まれてもアウトだ。
体内に侵入した後、病原性タンパク質は血液、リンパ、細胞間液を通じて全身に伝播する。分子サイズは大きいが、一旦分解された後に再結合したり、侵入を防ぐ組織それ自体を侵食したりすることで通り抜けていくのだ。この過程で免疫細胞と結合するため、免疫機能がこのタンパク質を排除することができない。
さらに、血管を侵食して広がっていく性質から、脳への異物侵入を防ぐ冠門も役に立たない。脳につながる門を閉めても、門や壁その物を取り込んで入り込んでくるような物だ。
このタンパク質が人体に入り込んだ場合に起こる症状について、榊は完璧に記憶していた。
感染してから約12~24時間程度で、高熱、関節痛、のどの痛み、頭痛といったインフルエンザ様の症状に加え、全身の激しい痛痒感が引き起こされる。その後、意識障害、痙攣、うわごと、譫妄の症状が生じるようになる。
全身の皮膚組織(主に顔面、胸部、手足)には、散発性の細胞壊死が発生する。主な症状は浮腫、紫斑、水疱や血疱、陥凹性壊死など。壊死性筋膜炎に類似した外見を呈するが、組織の破壊は真皮~脂肪組織までにとどまり、筋肉組織は維持されることが多い。
端的に言ってしまうと、感染した者は体の表面が生きながら腐れ落ちていくということだ。第2研究室に保管されている記録の写真やサンプルの姿は、目を覆わんばかりの有様で、初めて見た時に榊も気分が悪くなった。
感染による変異は体の表面ばかりでなく、血液および血管構造にも及んでいく。血液は黒化して粘度がグリセリンと同程度の約1500になり、赤血球の酸素含有量が著しく上昇する。血液の粘性の上昇によって心臓から送り出される血量が減少する代わりに、循環機能は強化された血管運動によって維持される。肝臓及び腎臓の機能は低下するが、老廃物は血管外に直接排出されるようになり、変異による神経系および筋肉系への異常は生じない。
血液粘性の増加によって、感染者は外傷に起因する出血量が非常に少なくなる。さらに、循環の多くが血管運動によって行われることで、主要循環器系の損傷へ高い耐性を獲得することになる。
感染した者は生きながら腐り落ち、血液はヘドロのようになって体中から悪臭を発し、それでいて死ぬこともままならなくなる。まさに地獄といえる。
顕著な症状が確認出来るようになってから2~5時間以内に、感染者は短時間の昏睡状態に陥る。この状態では心拍数は20分に1回未満、体温は外気と同一となり、この時点で以て完全に回復不能の状態になったと判断される。この活動停止状態は「休眠」、あるいは「一時的死」と呼ばれ、この間に皮膚組織の壊死と循環器系機能の再構築が急激に進行する。2~3時間程度の休眠状態を経た後、感染者は覚醒して活動を再開する。
「覚醒して活動を再開する」。これがこの病気の最悪な部分だ。感染から数時間で死ぬ病気は危険ではあるが、感染症としての脅威度は低い。他人に感染させる前に死ぬので、社会に広がりにくいからだ。伝染病が脅威になるのは、感染した人間が死ぬか治るかする前に動き回る猶予がある場合だ。
榊はモニターに手を伸ばし、表示されているモデルに手を触れた。これを作ったのは確かにかなりの大仕事だが、世の中に公表されることはあり得ない。それが正しい。これに関する情報は、一切外に出されるべきではない。
屍病



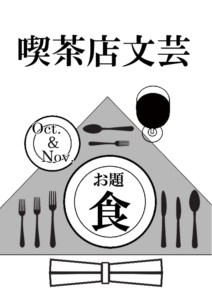

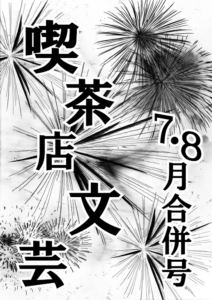
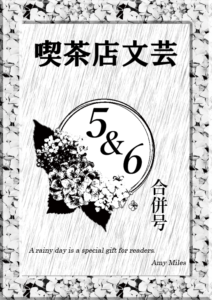


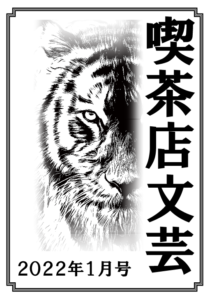
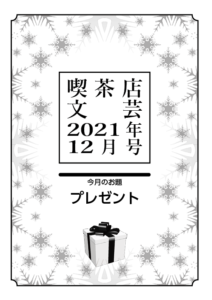
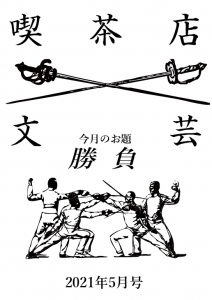
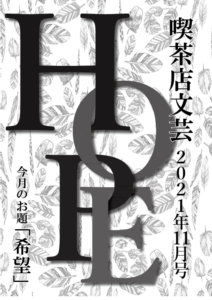
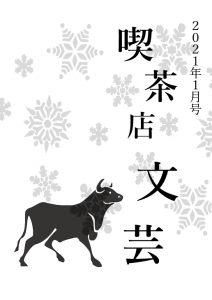
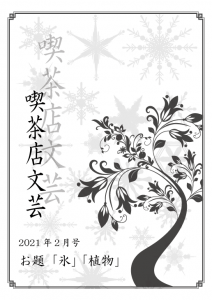
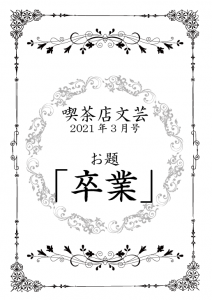
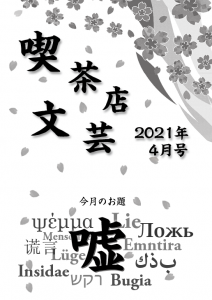
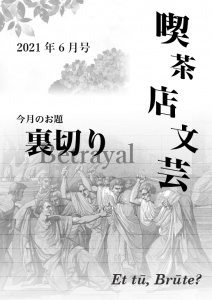
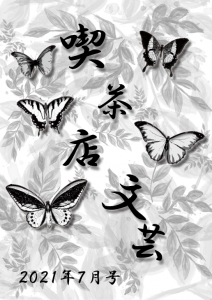
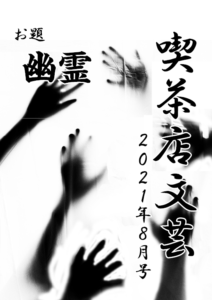

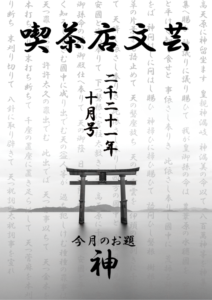
コメント